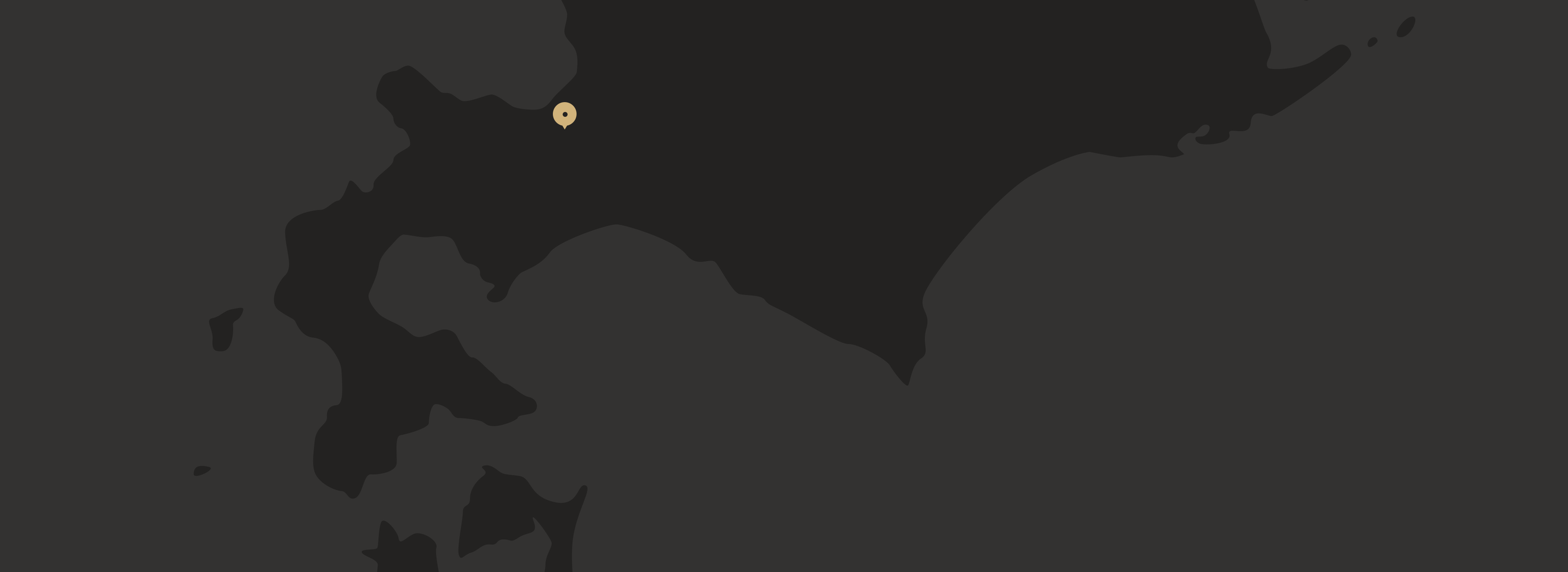Reservation查詢・預訂客房
航空券付きプラン
提携法人専用予約
2025.03.05
用世代相傳的“英式黑咖喱”和世界的杯子度過溫暖的片刻時光
NEIGHBORS

伴隨著1970年代起就在咖啡館喝咖啡的文化,“深度烘焙”和“自家烘焙”等辭彙開始流傳至今的城市——札幌。
伴隨著咖啡飄散的香氣,提供舒適空間的店鋪有很多,從歷經時代依然保持著不變的氛圍和味道的茶館,到不斷磨練味道和技藝的自家烘焙咖啡店,再到把握時代和需求不斷變化的店鋪,以各種各樣的風格迎接著來訪的客人。
被家人般愛戴的店主經營的店

從地鐵“西11丁目站”步行5分鐘,沿著有軌電車行駛的街道,它位於建築物的二樓,商店的名字是“Coffee gallery Clement (咖啡畫廊Clement) ”。
1987 (昭和62) 年在圓山地區開業,經過在重生為現在的“Kokonosukino”之前的“Robinson百貨店札幌”“Suskinorafira”的營業後來到了這個場所。掛在牆上的皮革招牌上刻著的“Clement”字樣非常惹眼。

走進店內,圍繞著中央的大桌子設置了桌席和吧臺席位,溫暖的照明營造出寧靜祥和的空間。店主以插花“嵯峨禦流”為代表,親自插上的迎花極具存在感。
常來店裡的人像父親和祖父一樣愛慕的店主,古屋嘉章經營的店裡,祖孫三代都有客人光顧。我將向您展示我走上咖啡館之路的經過以及我所喜愛的商店的魅力。
從與師傅的相遇到咖啡館之路

店主古屋先生從事情的開始就花了很長時間為我們娓娓道來
「這裡是我師傅的店。」
邊說邊遞過來的是寫著「咖啡雷羅」的令人懷唸的火柴盒。該商店於1962年開業 (昭和37年),是該市7家商店中的1家商店。這家店距離古屋先生當時居住的家只有3分鐘的步行路程,在這家店裡,我遇見了後來被稱為“師傅”的大山邦彥先生。
「初中的時候,第一次跟著媽媽買東西回來,一個人去是到了高中以後。當時的《少年Jump》《Sunday》等漫畫書一應俱全的店。」
據說有一次,大山對獨自來訪的古屋直截了當地說:「自己又不掙錢,還能悠閒地坐著喝茶。」。

雖然我對當時拋出的話感到驚訝,但我從心底想到了Furuya先生,“我不能做壞事”,我逐漸對如何面對大山先生用愛責罵的人感興趣就像擁有它一樣。在那之後,我自願作為兼職工作。
在師傅的指導下積累了經驗的古屋說,遲到自不必說,粗魯地使用餐具,不考慮別人只優先自己的時候,特別嚴格。對師傅的向往,客人喜歡的經驗,以及“喜歡學習和告訴別人”的想法,經過不斷的修行,終於擁有了自己的店鋪。
精心制作的“英式黑咖喱”

Oyama先生再現了札幌西餐廳廚師教授的味道,商店提供的菜單是“英式黑色 (黑色) 咖喱”。古屋繼承了這種味道,現在已經成為“Coffee gallery Clement”代名詞的招牌菜品。從大山先生的時代算起,這個咖喱積累了超過60年的歷史。
「首先在烤焦黃油和低筋面粉之前,一直持續炒30分鐘。因為會冒出很多煙,所以要看清裡面的東西,炒好之後要立刻倒入水,停止“烤”以免變成炭。然後,加入香料制作基礎的黃油面醬。」
這個“打底的方法”從大山制作時就沒有改變。在後半部分,據說在使用的材料中添加了一些古屋獨有的安排,例如將肉和洋蔥,甜酒“Orize”,蘋果汁,水果chatune,低聚糖煮沸。

“Clement風味煎蛋卷 (加咖喱) ”。午餐菜單有沙拉、味增湯、雪糕
幾乎不使用水和砂糖,最後與黃油面醬混合,有光澤後完成。這種“黑色”的原因是由於花費超過8小時的時間和精力而產生的。
“英式黑咖喱”在店內燈光的照射下,增添了光澤感。美味,然後在微微感覺到的甜味深處慢慢擴散的香料。想要充分品嘗黑咖喱本身味道的人,請品嘗王道的“咖喱”。
點了包著芝士和火腿的“Clement風煎蛋卷”,因為可以選擇咖喱作為醬汁,所以可以一邊感受與雞蛋的調和,一邊享受更加醇厚的味道。
像藝術品一樣的“世界之杯”

可以根據當時的喜好和心情選擇杯子 (擁擠的午餐時間除外)
“Coffee gallery Clement”的魅力不僅限於咖喱。
隔著吧臺對面的架子上一字排開的是從國內外收集來的超過120位客人的杯子&茶托。它美麗而有序的外觀就像藝術作品一樣。
以撥動古屋先生心絃的國內外器皿為代表,還有大正時代東洋陶器 (現在的TOTO) 制作的器皿、Noritake引以為豪的100年器皿、最上層還有與之有緣的札幌近郊的作家制作的陶器制器皿等,都是有著各自不同淵源與故事的充滿個性的杯子。
「說的話要花兩個小時。」古屋雖然笑著說,但關於杯子的誕生、歷史、材質等,只要時間允許,她都會滔滔不絕。

大受歡迎的“Imperial poselin (羅蒙諾索夫) ”是擁有270年以上歷史的深受俄羅斯皇帝喜愛的品牌。
當被問及這種“咖啡畫廊Clement”咖啡的特點時,古屋先生說:「我家是“昭和咖啡”,又深又苦,很濃。」。直接品嘗在札幌創業超過50年的“自家烘焙咖啡的店藏人 (Claude) ”的咖啡豆。為了混合,我們進一步混合並提供“札幌Wesima咖啡”豆。
根據杯子形狀的不同,泡咖啡或紅茶時香味的擴散方式和口感也各不相同。在為自己選擇杯子的優雅時刻,旅行的疲憊似乎會飛到某個地方。
反映季節的甜點

用特殊模具制作的“Shimaenga的panna cotta”
襯托咖啡和紅茶美味的時令甜點也不容錯過。我想在寒冷的季節享受它,“雪仙子”“Shimaenga的pannakota”只在每年的“札幌冰雪節”期間提供。看著它可愛的樣子,讓你無法通過勺子,你的心就會平靜下來。

店裡最受歡迎的“南瓜忌廉芝士蛋糕”
在即將到來的溫暖季節,夏季出現的“南瓜忌廉芝士蛋糕”似乎是使用整個蒸南瓜最受歡迎的甜點。
春天的櫻花,秋天的栗子,映照出不同季節的“Coffee gallery Clement”的一盤。每次我去,我都會等待下一個季節的到來。
我們將提供超越“美味”的價值

在後面的單間裡,偶爾也作為畫廊空間進行作家的展示
「當然,在一個可以放松的地方提供美味的東西以及咖啡店是很自然的,但它可能會持續很長時間,因為它增加了加上alpha的附加值。在我們這裡,它是“連接人與人”。」
「我遇到了各種各樣的人並成為了熟人。咨詢,有時依賴。我覺得沒有比這更有趣的買賣了。」
古屋雖然不斷遷移,但仍花費約40年時間孜孜不倦地創造出獨特的空間,追求各自熟悉的味道以及家庭般的溫暖,如今也聚集了超越世代、有著不同背景的人。
Coffee gallery Clement(コーヒーギャラリークレメント)
住所:北海道札幌市中央区南1条西13 フナコシヤ南一条ビル 2階
電話番号:011-242-9106
アクセス:地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩5分
SNS:https://www.instagram.com/clement_9106/
*請查看上面的連結以了解營業時間和定期休息日的詳細資訊。